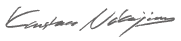同市にて木津川アートが開催、取り壊される銀行や、歴史ある建物にて現代アートの展示イベントに参加、皮肉にもその大仏鉄道跡地は展示会場の一つに。梶ケ谷トンネルの南は開発のされない田園風景、北には以前は田園であったが休耕地になっていた場所に高さ6.5mのギロチンを設置。写真のように北側からはギロチンのアーチとトンネルがシンクロし、田園風景が見える。
風にそよぐ金色の稲穂、縦横無尽に空を舞うオオタカ、闇夜を照らす蛍の群れー。かつてトンネルの向こうにあった鹿背山の原風景です。都市計画に基づく宅地開発が急速に進むにつれ、水田は閉散とした休耕地に姿を変え、オオタカや蛍は住処を追われました。トンネルのアーチをカンバスに見立て、「田舎の名画」を鑑賞した思い出が消え去ろうとしています。経済のグローバル化や少子高齢化の進展などを背景に、国の経済成長は鈍化しています。私たちは資本主義が生み出す「豊かさ」を享受しようと、限りある資源を食いつぶし、もがき続けています。日常に埋もれた「豊かさ」の本質を見失いながら。生物多様性の保全について世界的な協議が行われる中、鹿背山のような過疎化地では開発の手が緩む気配はありません。機械で野山を切り開いて手に入れたモノからは二度とこの風景は臨めないはずなのに。
断頭台のアーチをのぞき、鹿背山の未来に思いをめぐらせてください。
-
南には残る田園風景
-
 北には開発予定の休耕田
北には開発予定の休耕田

---それから約1年後、2011年12月17日 朝日新聞
大仏鉄道、遺構残った。ファン要望で開発計画変更明治時代に奈良・東大寺への参拝客を運んだ通称「大仏鉄道」の遺構が、京都府木津川市で現状のまま残ることになった。関西文化学術研究都市(学研都市)の造成地にかかり、撤去か移設が検討されていた。しかし、地元の要望や廃線跡が散策路として親しまれている実情を踏まえ、行政側が計画を見直した。大仏鉄道(大仏線)は1898(明治31)年、当時の私鉄・関西鉄道が現在のJR関西線加茂駅と東大寺近くにあった大仏駅間の8.8キロに開業。だが、蒸気機関車が走るには急勾配の山越え区間があり、加茂―木津―奈良を結ぶ現在の平坦(へいたん)線が9年後に開通すると廃線になった。
その遺構は木津川市から奈良市にかけて約20カ所に残っている。撤去を免れた遺構は、線路を支えた赤れんが造りの橋台「赤橋」と、線路の土台に造られた農業用水路の「梶ケ谷隧道(ずいどう)」。二つの遺構の上を通る線路跡は、のちに幅約3メートルの市道になった。だが、学研都市の開発区域にかかり、1995年の都市計画決定で道路 幅を12メートルにまで広げることに。開発にあたる都市再生機構(UR)は、道路を拡幅するには土台から造成し直す必要があり、遺構は撤去するか一部を残して移すかを検討してきた。
これに対し、地元の鉄道愛好家らでつくる「大仏鉄道研究会」などが「幻の鉄路を伝える貴重な歴史遺産」と保存を求めた。これを受け、URは遺構の前後の約300メートル区間は道路を迂回(うかい)させ、遊歩道にしてもよいという案を木津川市に示した。市の都市計画審議会は今年8月、計画変更を認めた。URの申請を受け、国土交通省も来春には認可する見通しだ。ハイキングの季節には遺構を訪ねる人も多く、地元にとっては観光資源になっている。保存を訴えてきた市民団体「鹿背山(かせやま)の大仏鉄道遺産に親しむ会」メンバーの森本茂さん(58)は「保存は難しいと思っていたのでうれしい。日本の鉄道が近代化へ向かう過程を示す地域の文化遺産を大切にしたい」と喜んでいる。(横川修)
---突然の保存決定の記事は関係者を奮い立たせた。2010年11月から2012年8月の開発が始まるまで、茶色く錆びたギロチンはトンネルの向こうの田園風景を見つめ続けた。